後期高齢者医療保険料
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得割額の合計額を個人毎に計算し、7月に1年間分の保険料が決定します。ただし年度途中で、75歳になった場合や他府県から転入された場合、亡くなられた場合は年額を月割で計算します。
所得割額のもとになる総所得金額は、賦課年度の前年の所得です。(このため、前年の所得が確定していない4月などは仮徴収となります。)また、他府県からの転入の場合は所得の確認がすぐにできないことから、あとで所得割が加算されることがあります。
もし、ご自身の後期高齢者医療制度の保険料をお知りになりたい場合は、
滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算できますので、こちらをご利用ください。(別ウインドウで開く)
(所得割および賦課限度額の激変緩和措置には対応しておりません。予めご了承ください。)
令和6・7年度の保険料率(年額)
令和6年4月1日から保険料率を改定します。
| 区分 | 保険料率 | |
| 令和4・5年度 | 令和6・7年度 | |
| 被保険者均等割額 | 46,160円 | 48,604円 |
| 所得割率 | 8.70% | 9.56% (注1) |
| 賦課限度額 | 66万円 | 80万円 (注2) |
※「所得割額」の計算方法:総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の所得割率
ただし、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合のみ差し引くことができます。
注1 所得割の激変緩和措置について
(総所得金額等-43万円)が58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率は8.84%となります。
注2 賦課限度額の激変緩和措置について
令和6年3月31日以前から後期高齢者医療保険の被保険者であった方、もしくは障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者となった方は、令和6年度に限り賦課限度額は73万円となります。
(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後滋賀県外へ転出した場合は対象外となります。)
令和6年度の保険料金決定について
令和6年度の保険料金は、令和6年7月中旬に郵便でお知らせします。
保険料の軽減について
賦課期日(4月1日)または資格取得日現在での被保険者と世帯主の所得の合計額などにより均等割額、一定の条件の所得割額が軽減されます。この場合の所得は、65歳以上の方の公的年金等に係る所得については最大15万円を控除し、専従者控除や土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除の適用前で計算します。
均等割額の軽減割合
- 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が【43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)】以下
→7割 - 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が【43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)】以下
→5割 - 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が【43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)】以下
→2割
※年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える方、または65歳以上で公的年金等収入額125万円を超える方が該当します
被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった方の軽減
所得割はかからず、均等割は5割軽減。ただし、均等割額の軽減は、資格取得後2年を経過する月までです。
保険料の納め方
保険料の納め方は特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書による納付、または口座振替)の2種類に分かれます。
基礎年金等から特別徴収される場合、年度のうち、4・6・8月は、その年の2月の保険料の金額で仮徴収し、7月に確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を、10月・12月・2月の3回で徴収します。
また、保険料特別徴収中止申請により年金からの天引きから、口座振替に変更できます。ご希望の方は、保険証と通帳と金融機関の届出印を持って窓口にお越しください。
添付ファイル
保険料特別徴収中止申請 (PDFファイル: 262.1KB)
以下の方は、特別徴収ができません。
- 年金が年額18万円未満の方
- 加入や転入されて半年までの方
- 保険料額が途中で減額になった方
- 介護保険料が天引きされていない方
- 介護保険料との合算額が、天引きしようとする基礎年金等の金額の2分の1以上の方
(特に、複数の年金を受給されている場合はご注意ください。)
年度当初(7月)は普通徴収の場合、保険料の額の「通知書」と、お支払いただく「納付書」は、別送しております。通知書と納付書の到着が前後する場合がございますのでご了承ください。また、納付書は年間分を一度にお送りしますが、各納期までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアで、お支払ください。
保険料(普通徴収)の納付場所
- 彦根市役所、支所、出張所
- 取扱金融機関(金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
滋賀銀行、りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局) - コンビニエンスストア(順不同)
セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ディリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラグループ、コミュニティストア - スマートフォンアプリ(PayB、LINE、楽天銀行、PayPay、au Pay、J‐Coin Pay) 他
※コンビニエンスストアでは、金額が30万円を超えるもの、収納用バーコードがないもの、金額を訂正されたもの、納期限が過ぎたものはお取り扱いできません。
所得税などの申告時の社会保険料控除について
年金から天引きされる分は、本人以外の社会保険料控除の対象になりません。国民健康保険と同様に世帯主の方が納められる場合は、保険料特別徴収中止申請により特別徴収を口座振替に変更する必要があります。
添付ファイル
保険料特別徴収中止申請 (PDFファイル: 262.1KB)
保険料の納付はお早めに!
後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、7月から翌年3月までの9期に分割し、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料 100円」や「延滞金」が加算されます。なお、どうしても納付が困難な場合(災害や病気、その他特別な事情がある場合など)は、猶予制度を受けられる場合がありますので、そのままにせず、早めに「債権管理課(0749-30-6109)」までご相談ください。
未納者の取り扱い
特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。
- 被保険者証を返していただきます。
定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、有効期限が短い「短期被保険者証」の交付、または被保険者証を返していただき、代わりに資格証明書の交付となります。資格証明書の場合、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。 - 保険給付が差し止めになります。
保険給付の全部、または一部が差し止めになります。 - 保険給付の額から滞納分の保険料を控除します。
(2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険料を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険料が差し引かれます。 - 法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産などの)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
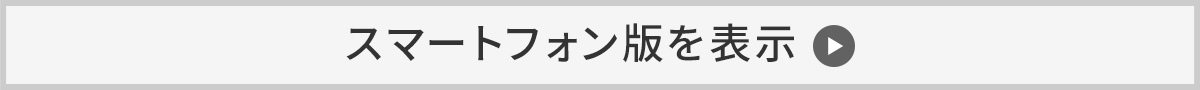







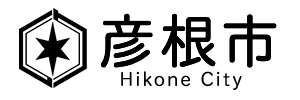
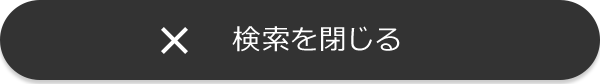
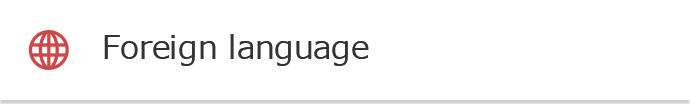
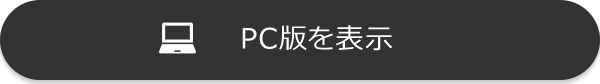
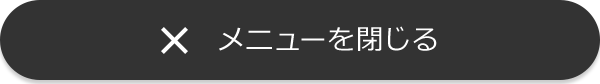
更新日:2024年03月28日