中山道・高宮宿場町
高宮宿場町
- 江戸より第六十四宿、百十九里十六丁(約474キロメートル)
- 京へ十六里六町(約64キロメートル)
鳥居本宿から約6キロメートル。その間、「芭蕉の昼寝塚」や万葉集に登場する鳥籠山と芹川など、古道を歩くにふさわしい歴史を語ってくれます。高宮宿は、いまも多賀大社への大鳥居をシンボルとして、商店街が立ち並ぶ活気ある町。そのたたずまいには、江戸期栄えた宿場町としての名残あるウダツや袖壁のある商家や民家が連なりを見せています。
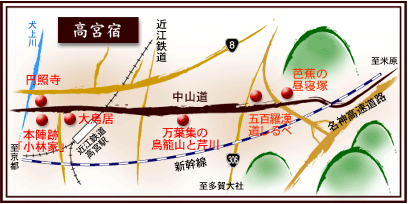
五百羅漢への道しるべ
鳥居本宿から南に進むにしたがい彦根城下に近づきます。原町の外れ、国道306号と交わる所に八幡宮があり、その境内には芭蕉の昼寝塚という小さな石碑が残っています。街道沿いには、井伊直弼の供養塔がある天寧寺五百らかんへの道標も立っています。

万葉集の芹川と大堀山
大堀町に入り、芹川の橋に着きます。左の小高い丘は大堀山といいますが、鳥籠山(トコノヤマ)という説があり、そばを流れる芹川は、万葉集では不知哉川(イサヤガワ)と呼ばれたようです。
近江路の 鳥籠(トコ)の山なる 不知哉川
日のこのごろは 恋つつもあらむ

多賀大社への大鳥居
町並みの中央あたりに、高さ11メートルの多賀大社、一の鳥居が宿場町のシンボルのように立っています。また、その右傍らには、「是より多賀みち」の小さな道しるべと、かって多賀みちを照らした常夜燈が並んで立っています。これより約3キロメートル余の行く先には、延命長寿と縁結びの神として崇められる多賀大社があります。

三光山円照寺
高宮家家臣の北川九兵衛が剃髪建立。境内には明治天皇ゆかりの「止鑾の松」という名の松の大木や「家康公腰懸石」があります。

旧本陣跡
円照寺の向かいにある門構えのある家が、本陣跡の小林家です。

芭蕉の紙子塚





更新日:2024年09月02日