市街地再開発~四番町スクエア
TRADITIONAL&FUTURE
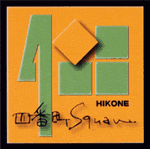
四番町は、明治12年~昭和44年の町名・大字名です。
江戸時代から続く「白壁町・内大工町・寺町」が合併して成立し、明治22年犬上郡彦根町の大字となり、昭和12年に彦根市四番町となりました。昭和44年、住居表示の実施により、現行の中央町・本町一丁目の一部となり、彦根の台所と呼ばれた市場商店街を中心に地元の人々に親しまれてきました。
「四番町スクエア」は、国宝彦根城や夢京橋キャッスルロードに隣接するエリアにあり、大正ロマン漂うまちとして21世紀に新しく生まれ変わろうとしています。
四番町スクエアまちづくりのあゆみ
再生にむけて
十数年の歳月をかけた再開発計画が諸処の事情により、衰退行き詰まり平成9年3月、彦根中心市街地再生事業委員会の提言を受ける形で、事業の見直しを余儀なくされるに至り、再生不可能のムードが大勢を占めるようになった。このような状況において、「このままでは本町市場商店街がゴーストタウンになってしまう」という強い危機感を抱いた若手の商店主たちが、平成8年に「檄の会」を結成。行政に頼らない自分たちの力だけで本町市場商店街を再生しようと活動を始めた。
「檄の会」では、夜を徹して通称D地区と呼んでいる地区(0.5ヘクタール)に商業集積を図るための研究を重ねたが、実態に合う事業手法が見つからない中、平成10年7月、建設省において「街なか再生土地区画整理事業」が創設され、対象となる最小面積が0.5ヘクタール以上に設定されたことや、区画道路にかかる移転移設費などの整備費が事業対象になったことから、居住者対策などを含めてA・B・C・D地区(1.3ヘクタール)に拡大して実現可能な計画づくりが進められるようになった。
彦根市本町土地区画整理事業 四番町スクエア‐まちづくりへの考え方
まちづくり協定(景観ルールブック)
古きよき伝統を、未来へつなげるまち
彦根市本町地区の街づくり構想を具現化する上で、古きよき伝統を、未来へつなげる街〈Traditional & Future〉の景観イメージ、建築様式を取り入れて、街全体で統一感のとれた魅力的な景観づくりを行います。
近江の東玄関、彦根は、関ヶ原の合戦後、初代彦根藩主、井伊直政が、実権を握り、井伊家三五万石の居城として栄え、経済、文化の中心的存在であり、中世から近世に掛けての、貴重な歴史遺産を数多く残しています。又、開国を英断し、今日の日本の礎をつくった井伊直弼を育てた彦根は、武とともに風雅を尊ぶ土地柄でもあり、武具、武器の製作にたずさわった塗師、指物師、飾り金具師などが、平和産業としての仏壇製造に転向し現代に、技術と伝統が引き継がれています。
このような時代背景と、彦根市ならではの建築様式を生み出し、50年後、100年後を見越すまちづくりの方法が、明治、大正時代のディティール(擬洋風建築)と、現代建築の融合であり、日本伝統技術をはじめ、彦根市地場産業、伝統、文化と最新技術との融合です。
それらを建築物のひとつとして取り入れていくことが、彦根市ならではの新しい建築になります。
Romantic of the Taisho era
大正ロマン漂うまち
自由を謳歌した明治・大正の建築意匠と現代建築を融合したまちなみ景観である「大正浪漫」をコンセプトにデザインの共有をしています。
私たちは、大正時代の雰囲気を醸す新しい景観の中で、まちを感じとり、訪れる人にとっても何をどうすれば一番心地よいかを考えながら、暮らしを求めまた、商いを求めてゆきたいと思います。
そうすることが結果として、よりいっそう大正という時代を際だたせ、江戸時代の文化と西洋とが融合し、独自の文化を謳歌するダイナミズム溢れる四番町スクエアが誕生するのだと考えています。
福祉のあるまちづくり基準
ユニバーサルデザイン
近年、より豊かな社会の実現にむけて、バリアフリーという言葉をよく耳にします。私たちは、人に優しいまちづくりを、そして、人々が積極的にアプローチしてゆくまちづくりをめざし、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れていきます。ユニバーサルデザインは、快適なまちづくり、人々が外に出る原動力となるでしょう。
豊かさを求めて
ユニバーサルデザインのまちとして
- やすらぎの空間をもつまち
- 助け合いのまち
- 自由に動ける迷いにくいまち
の3つを中心に揚げました。
1.やすらぎの空間をもつまち
- 楽しく、快適に過ごせる、豊かさを感じるまちをめざします。
- 疲れたら休める、憩える、世間話ができる場をつくり、積極的な情報交換がおこなわれることに期待します。
2.助け合いのまち
- 休める場所、世間話ができる場所として設置された授乳場所や託児所、休憩所などは、集まる人々が互いに知恵を出し合い、助け合う場となります。しかし、施設だけでは、実現しません。声を掛け合う習慣を身につけることが大切だと思われます。
- そのためには、ハード面だけでなく、ソフト面での工夫が必要です。
- 例えば、お年寄りがまちを助ける仕組みをつくります。お年寄りがアルコーブ(入り込み)や公園、地蔵堂に出てきて、子供達をみたり知恵を貸したりします。誰もが役割を持つことで、他人から助けられていること、他人を助けなければならないことに気づくと思われます。
- また、そこに住む人々の視点を持ったまちづくりが大切です。そこに住む人々が豊かに生活していれば、訪れる人々もその豊かさを感じ取ることができると考えます。
3.自由に動ける迷いにくいまち
- 安全に通行できるを前提とし、
- どこへ行けばいいか直感的にわかることが大切だと考えています。
四番町スクエア
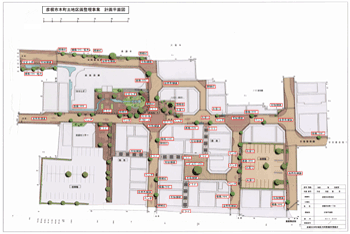




更新日:2024年09月02日