植物 荒神山の植生の移り変わり
約1万2千年前の植生花粉分析の結果から曽根沼の底には厚さ9メートルの泥炭層(ピート)が堆積しています。この泥炭層には植物の花粉が多数含まれており、この花粉を調べることにより、約1万2千年前から現在にいたるこの付近の植生の移り変わりを知ることができます。
- f帯 0~2.4メートル(0~約3,000年前)
暖帯林・マツ林・スギ林(アカガシ亜属・シイ-クリ属・スギ属・マツ属) - e帯 2.4~6.2メートル(約3,000年前~約6,300年前)
暖帯林(アカシア亜属・シイ-クリ属) - d帯 6.2~7.4メートル(約6,300年前~約8,600年前)
- 温帯林・暖帯林(コナラ亜属・エノキ-ムクノキ属・アカガシ亜属)、コウホネ・ハス・ヒシなどの水生植物も多くなります。
- c帯 7.4~7.8メートル(約8,600年前~約9,000年前)
温帯林・スギ林(コナラ亜属・ブナ属・スギ属) - b帯 7.8~9.0メートル(約9,000年前~約12,000年前)
温帯林(コナラ亜属・ブナ属・クマシデ属・カバノキ属) - a帯 9.0~9.5メートル(約12,000年前)氷河期
亜高山性針葉樹林(モミ属・ツガ属・トウヒ属・マツ属)
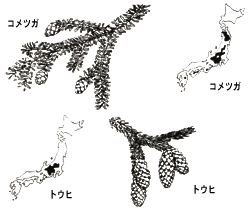
1万2千年前に曽根沼周辺に生息していた亜高山性針葉樹
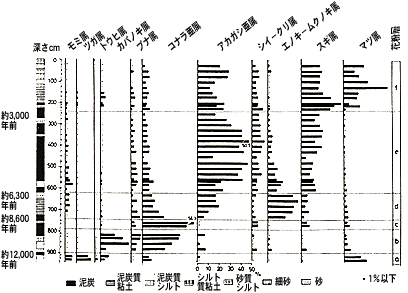
滋賀県彦根市曽根沼の花粉ダイアグラム
(松下・前田分析、石田志朗・竹村慧二
1984:彦根西部地域の地質、90ページ 第50図より改変)
花粉分析の結果から、この付近の植生はおそらく今から約1万2千年ほど前は亜高山性の針葉樹林(ウラジロモミ・コメツガ・トウヒ・シラビソなど現在は標高2,000メートルくらいの山地に分布)が優占し、気候的に寒冷な時期(氷河期)であったと推定できます。
それ以降は次第に気候が温暖になり、温帯林(ミズナラ・ブナ)→暖帯林(アカガシ・シイ)や河畔林(エノキ・ムクノキ)、アカマツ林へと植生が移り変わりました。
以前、荒神山のやせ尾根にアカモノという植物が生えていました。しかし現在は木が生い茂ったために生育は確認されていません。アカモノは亜高山帯に多く見られるツツジ科の低木で、荒神山のアカモノはやせ尾根という環境条件のきびしいところに生き残った氷河期の遺存種(かつては広く分布していたが、その後環境の条件などの変化で、分布範囲が当時の条件を保つ局地に取り残されたと推定される種。)であったと考えられます。
一般に、近畿地方の内陸平野では照葉樹林(暖帯林)の出現・拡大は7,500~8,000年前から急激にはじまり、温帯林と照葉樹林(暖帯林)の交代の時期には約6,000年前であるといわれています。
また、暖帯林の代表であるシイ林が約3,000年ほど前から人間(縄文人)の手で伐採され、シイに代わってアカマツが増えてきたこともこの花粉分析の結果から分かります。現在、このような自然植生の名残りをとどめるシイ林は唐崎神社(日夏町)や天満宮(清崎町)などの神社や荒神山の山裾に帯状に分布しています。荒神山神社の東側に分布しているタブ林もシイ林同様暖帯を代表する自然林(主に海岸地方に分布)のひとつで、シイ林よりも斜面の傾斜がゆるやかで肥沃な土壌の上に成立します。以上のことから、人類による自然破壊が盛んになる前(約3,000年前)は荒神山の山頂や傾斜のゆるやかな山腹にかけてはタブ林が、傾斜の急な山裾にはシイ林が分布していたと考えられます。
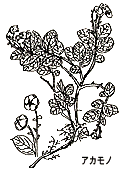
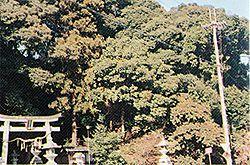
唐崎神社のシイ林
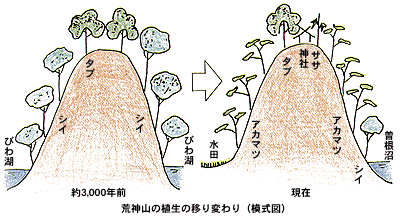




更新日:2024年09月02日